皆さんは、普段運動をされていますか?
毎日運動をしている方もいれば、様々な理由から運動が全くできて良な方もいると思います。
また、全く運動をしていない方であっても、運動の重要性を理解している方も多くいると思います。
そして、最も手軽で、すぐにでも始められる運動として、まず思い浮かぶのがウォーキングかと思います。
本記事は、普段運動しない方でも、「今日からウォーキングをしたい!」と思える内容となっていますので、ぜひ最後まで読んで頂ければと思います。
ウォーキングとは? 散歩とウォーキングの違い
まず、皆さんは、散歩とウォーキングの違いを知っていますか?
「正直、分からない」という方も多くいるかと思います。
散歩とウォーキングを、説明すると以下となります。
<散歩>
気晴らしや健康のために、ぶらぶらと歩くこと。散策。自由気ままに歩き回ること。
<ウォーキング>
健康の保持・増進やスポーツ感覚で行われる積極的な歩行運動。
上記のように、散歩は「気分転換」、ウォーキングは「健康保持・増進」と目的が異なります。
そんな散歩とウォーキングですが、どちらも「いつでも」「どこでも」「誰でも」行うことができるという利点があります。
そのため、目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。
そんな中、次の項目ではウォーキングの効果についてご紹介します。
こんなにあるの!?ウォーキングの効果
さて、「健康保持・増進」のために行うウォーキングですが、様々な効果があることが分かっています。
今から一覧でご紹介しますが、効果の多さに驚くこと間違いなしです。
ウォーキングには上記のような様々な効果があります。
それでは各効果について説明します。
※なお、「説明不要!」という方は、以下は飛ばして頂いて次項「ウォーキングの消費エネルギーについて」へお進みください。
高血圧の改善
血圧を下げる「タウリン」や「プロスタグランジン」という物質が増加することが理由です。
また、米国ミシガン州で行われた「ヘンリー フォード運動試験」の結果によると、6メッツ程度(きつめのウォーキング)の運動を続けて行っている人は、高血圧の発症リスクが30%減少し、12メッツ以上の運動を続けている人だと、発症リスクが50%低下したとのことです。
<メッツ>
身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当します。

心肺機能の強化
心肺機能とは、酸素を筋肉内の細胞に送り届ける作業のことを言います。
そして、酸素は脂肪やグリコーゲンを燃焼させるために必要となります。
なぜなら、人が運動を続けるためには、筋肉内で脂肪やグリコーゲンを燃焼させ、エネルギーを作る必要があるからです。
人が運動をすると、急速に酸素が使われるようになり、酸素不足の状態になります。
そのため、酸素不足の状態を何とかして解消するために、心肺機能が強化されます。
ウォーキングを続けることで、適度に酸素不足の状態を作り出すことができ、結果的に心肺機能の強化につながります。
<グリコーゲン>
摂取した糖を体内に貯蔵しやすいように変換したもの
また、余談ですが、ウォーキングをすることで、心血管疾患リスクを減少させることができます。
英国ケンブリッジ大学の研究によると、ウォーキングなどの運動をすることで、心血管疾患で死亡するリスクをほぼ3分の1も減らせるとのことです。
また、米国心臓学会(AHA)によるメタ分析によると、心臓発作や心臓突然死によるリスクを最大で50%も減少できるとのことです。
<心血管疾患>
心臓・血管などの循環器における疾患。「不整脈」や「虚血性心疾患」などがあります。
骨の強化
ウォーキングをすることで、骨に対して適度な刺激が与えられ、骨を強くするカルシウムの吸収が高まるからです。
骨には負荷がかかると、その不可に応じて骨自身を強くする仕組みがあります。
というのも、骨は負荷(刺激)を受けるとカルシウムが沈着しやすくなります。
また、ウォーキングを含む運動をすることで血流が良くなり、骨を作る骨芽細胞が活発になります。
そのため、ウォーキングをすることは「骨の強化」に繋がるのです。
加えて、日中に日光を浴びながらウォーキングをすることで、体内でビタミンDが生成されます。
このビタミンDはカルシウムの吸収を助ける働きがあるため、より「骨の強化」に繋がります。
なので、朝の時間帯、日が出てきてから運動することがオススメです。
肥満の解消
ウォーキングなどの有酸素運動は、体脂肪をエネルギー源として利用するため、肥満の解消となります。
仕組みは「心肺機能の強化」で説明したように、運動によって体内に酸素を取り込んで、脂肪をエネルギー源として燃やすからです。
なお、一般的にウォーキングなどの有酸素運動は、「20分以上継続して行わないと脂肪燃焼効果がない」という思われている方もみえますが、「20分以上継続して行うことで、脂肪燃焼効果が高まる」というのが正しいようです。
脂質異常症・動脈硬化の改善
血中の中性脂肪を分解する酵素である「リパーゼ」が活性するからと言われています。
<リパーゼ>
中性脂肪を遊離脂肪酸とグリセロールに分解する酵素。
要は脂肪を分解するもの。
肝機能の改善
食べすぎや運動不足によって中性脂肪が肝臓に多く蓄積してしまう「脂肪肝」という症状があります。
ウォーキングをすることで、脂肪が燃焼されることで、肝臓に中性脂肪が蓄積されること防げるため、「脂肪肝」になってしまうことを防ぐことができます。
また、「脂肪肝」となってしまっていてもウォーキングを続けることで、肝臓周りの脂肪がなくなり、肝臓機能が改善されます。
筑波大学医学医療系の正田純一教授の研究によると、「週250分以上(1日換算30分以上)」の運動を続けると肝臓にたまった脂肪が減りやすくなるとのことです。
<脂肪肝>
脂質の1つである中性脂肪が肝臓内に多く蓄積する状態のことです。
脂肪肝の怖い所は、無症状、つまり気が付かないうちに症状が進行するところです。
脂肪肝を放っておくと、いつの間にか「肝炎」→「肝硬変」→「肝がん」と進行していきます。
そのため、いかに脂肪肝にならないかが重要となります。
糖尿病の改善
ウォーキングを行うことで、血中のブドウ糖がエネルギーへ変換されることから、血糖値が下がります。
また、ウォーキングにより足回りを中心とした筋力が増えることで、インスリンの効果が高まり、血糖値が下がりやすくなります。(これをインスリン抵抗性の改善と言います。)
英国バーミンガム大学の調査によると、ウォーキングなどの運動をしている人は、最も運動量の多い人で、糖尿病リスクが25%減少し、少し運動していたという人でも12%減少していたとのことです。
また、ケンブリッジ大学とユニヴァーシティ カレッジ ロンドンの過去の研究によると、週に150分(1日に30分)のウォーキングなどの活発な運動を行っている人は、2型糖尿病のリスクが40%減少るとのことです。
<2型糖尿病>
インスリンの作用不足(インスリン抵抗性)により、血糖値が慢性的に高くなる病気で、糖尿病の一種です。
先天的に発症している1型糖尿病と違い、食生活の乱れや運動不足により後天的に発症する病気であるため、日ごろの食生活を正し、適度な運動を習慣的に行うことで、防げる病気です。
腰痛の改善
正しいフォームでウォーキングを行うことで、筋肉や関節可動域が高まり、結果的に腰痛改善につながります。
というのも、ウォーキングによって「腹筋」や「背筋」が鍛えられるからです。
「腹筋」は腰椎の前にある筋肉、「背筋」は腰椎の後ろ側にある筋肉です。
そして、「腰椎」とは、脊柱(せきちゅう:背骨のこと)の中でも、腰の骨当たりのことで「腹筋」と「背筋」を鍛えることで、「腰椎」をしっかりと支えることができるようになり、「腰痛の改善」に繋がります。
<ウォーキングの正しいフォーム>
リラックス効果
リラックス効果のある神経伝達物質であるセロトニンが分泌されます。
また、一定の動作をリズミカルに行うため、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果が期待できます。それにより自律神経の乱れが整ったりする効果も期待できます。
気分の高揚・自己肯定感の向上
エンドルフィンやドーパミン、セロトニン、テストステロン、トリプトファン等の神経伝達物質が作られることで、気分の高揚や、自己肯定感の向上といった効果があります。
また、米国のハーバード公衆衛生大学院の研究によると、1日35分のウォーキングをすることで、うつ病のリスクの発症リスクが17%低下するとのことです。
もちろん、うつ病を発症してしまっている人にも、ウォーキングは効果はありますので、無理をしない程度に取り組んでみてはいかがでしょうか。
<エンドルフィン>
気分の高揚や、幸せ感が得られる神経伝達物質です。
また、モルヒネの数倍の鎮痛効果があります。
<ドーパミン>
やる気を促したり、幸福感をアップさせる神経伝達物質です。
<セロトニン>
ドーパミンやノルアドレナリン(恐怖や驚きなど)をコントロールし、精神を安定させることに一役かっている神経伝達物質です。
セロトニンが増えることで、慢性的ストレスや疲労、イライラ感、向上心の低下、意欲の低下等を防ぐことができます。
<テストステロン>
男性にとっては、別名モテホルモンと言われています。
筋肉量が増加したり、男性らしい太い骨格になったり、男らしさの向上に非常に有効な物質です。
行動力の源泉ともなるため、生き生きとした人生を謳歌するためにも必須の神経伝達物質です。
<トリプトファン>
幸せホルモンである「セロトニン」を作り出す、唯一のアミノ酸と言われています。
不眠の解消 · 精神安定効果 · アンチエイジング · 鎮痛効果 · 集中力・記憶力の向上等々が挙げられます。
脳への血流アップ
運動することで、全身の血流がアップします。
もちろん脳への血流量もアップします。
そのため、頭がスッキリしたり、集中力の向上につながります。
また、ストレスによる頭痛の解消にもつながります。
記憶力の向上
記憶を司る海馬に、脳由来神経栄養因子というタンパク質を作る前の遺伝子が沢山出来ることが判明しているとのことです。
また、オランダのラドバウド大学医療センター ドンデルス脳研究所によると、記憶作業の2時間後にウォーキングなどの運動をすると、記憶力が10%向上することが明らかになりました。
ウォーキングは、認知症や記憶力の低下の予防、学習能力のキープにも役立つようです。
血管を丈夫にする
筋肉から「ブラジキニン」という物質が放出されます。この「ブラジキニン」が血管内皮細胞を活性化させてNO(一酸化窒素)の産生を促すことが分かっています。
<NO(一酸化窒素)>
血管内皮細胞を修復して血管をしなやかに広げる働きや、プラーク(血管内のこぶ)を予防する働きなどによって、動脈硬化の進行を妨げる物質です。
うつ病リスクの低下
「気分の高揚・自己肯定感の向上」でも説明しましたが、ウォーキングをすることで、うつ病リスクの低下が期待できます。
米国のハーバード公衆衛生大学院の研究によると、1日35分のウォーキングをすることで、うつ病のリスクの発症リスクが17%低下とのことです。
また別の研究では、週150分(1日30分)の活発なウォーキングに相当する運動を日常的に行うことで、うつ病リスクを25%減少させることができるとのことです。
ウォーキングの消費エネルギーについて
先ほど、「高血圧の改善」にて厚生労働省の資料をお見せしましたが、それと合わせて確認すると、
- ほどほどの速さでのウォーキング(4.5~5.1km/時)=3.5METS
- 速いウォーキング(5.6km/時)=4.3METS
- とても速いウォーキング(6.4km/時)=5.0METS
上記となります。
そのうえで、消費カロリーを計算するためには以下の計算式に当てはめる必要があります。
〇 METS × 時間 × 体重 × 1.05 = 消費kcal
例えば、体重60kgの人が1時間、ほどほどの速さでウォーキングを行った場合
「3.5METS × 1時間 × 60kg × 1.05 = 220.5kcal」となります。
ちなみに、「1kg ≒ 7,000kcal」 であるため、毎日ウォーキング行った場合、1kg落とすために1ヶ月の時間を要することとなります。
ただ、ウォーキングを行うことで、心肺機能が向上したり、筋力が向上するとことで、普段の消費カロリーが増加することで、何もしないよりは痩せやすくなります。
ウォーキングに関する参考図書
ここまで読み進めて頂き、ありがとうございます!
最後に「ウォーキングに関する参考図書」をご紹介します。
①やせる! ウォーキング
まず、ご紹介するのは、長坂靖子さん著の「やせる! ウォーキング」です。
カラーの図解が印象的で、内容も非常に分かりやすいです。
また、ウォーキングをする際の正しい姿勢や、注意事項といった内容もしっかりと記載があり、痒いところに手が届くような内容になっています。
②楽しく歩いて若返る!大人のウォーキング
次にご紹介するのは、マキノ出版から「楽しく歩いて若返る!大人のウォーキング」です。
こちらも、先ほど紹介した「やせる! ウォーキング」のように、カラーの図解があり、分かりやすい内容となっています。
ただ、「やせる! ウォーキング」に比べて少しボリュームにかける所があり、もう少し内容が欲しいなと感じました。
③ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方
3つ目にご紹介するのは能勢博さん著の「ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方」です。
こちらは、先ほど紹介した2冊とは異なり、学問的な見地からウォーキングについて解説された書籍となります。
そのため、「正しいウォーキングを知りたい」いった要望には少し沿わないとです。
ただ、ウォーキングについてもっと深く理解した時にオススメの一冊です。
④マンガでわかる神経伝達物質の働き
最後にご紹介するのは、野口哲典さん著の「マンガでわかる神経伝達物質の働き」です。
ウォーキングとは異なりますが、「こんなにあるの!?ウォーキングの効果」でご紹介した神経伝達物質について理解を深めるためにオススメの書籍です。
可愛らしいイラストで描かれていますが、内容はしっかりしていますので、読み物としてもオススメできる一冊です。




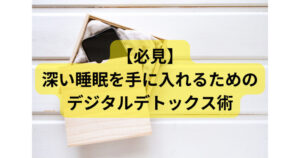

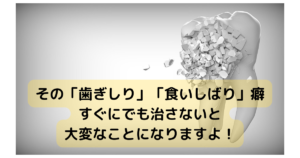

コメント